 このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を
このコーナーでは飼主のみなさまと動物に役立つ情報を
お伝えして行きたいと考えています。楽しみにしていてください。
※「矢印」をクリックすると他の記事も読めます。
高齢猫のお世話の方法
<寝たきりになった高齢猫の介助>
猫ちゃんが動けず寝たきりになったり、老衰や病気で食事が上手く取れなくなった場合に必要なことをまとめてみました。
1)食事の介護:強制給餌
食器から自力で食事が取れなくなったら、伏せの姿勢にして、食べやすいペースト状のフードを手で少しずつ口の前に運んで与えてください。自力でペロペロを舐めるように食べてくれたらOKです。自力で舐めなかったり、いつまでも口の中にフードが残っているような状況になったら強制給餌を始める時期です。
強制給餌とは、病気などで一時的に食欲がない動物や、老齢のため自力で食べ物を食べられなくなった動物を介助する目的で、ペースト状にしたフードを注射ポンプを使って口の中に流し込んで食事を与える方法です。
<準備するもの>
- 毛布 : 猫ちゃんがゴソゴソ動かないように、または落ち着かせるために、猫ちゃんの体全体を包み込むように(巻くように)して使う。
- エリザベス・カラー : おとなしい、または弱っていてあまり動かない猫ちゃんは、強制給餌をしている時に前足が邪魔にならないように(出てこないように)エリザベス・カラーを逆向きにはめて前足をブロックするように使う。
- ムース/ペースト状にした流動食 : ドラフードをふやかしたものや、ウエット系フードをミキサーなどでペースト状にした流動食を事前に作っておく。動物病院などでも、流動食として利用できる製品(A/D缶、リキッドタイプの商品)が販売されているので、それらを利用するのも良いでしょう。
- 注射ポンプ:1〜10mlまでのサイズの注射ポンプ。猫ちゃんの食事摂取量や強制給餌のスキルに応じてサイズを選んでください。
(注射ポンプは当院でおわけいたしますのでお申し出ください) - 濡れたタオル、ウエットティッシュ:口の周りの汚れを拭き取るために
<強制給餌の方法>
- 注射ポンプに流動食を詰めたものを数本用意します。
- 強制給餌を行う時は2人1組で行うのが基本です。1人は動物を支える保定係、1人が給餌を実施する係です。
- ゴソゴソと動く猫ちゃんに対しては、保定しやすくする事と落ち着かせる目的で、優しく全身をタオルで巻きます。
- 強制給餌を行なっている時に、口からフードをこぼして汚してしまう猫ちゃんには、前掛けをして汚れるのを予防してあげると良いでしょう。
- 強制給餌を行う時の姿勢は、猫ちゃんの顎を少し持ち上げた形(顔が45度くらい上に向いている状態)で保定します。
- ペースト状の流動食が入った注射ポンプを犬歯のすぐ後から(犬歯と奥歯の間には歯が生えてないスペースがあります)喉の方向に向けて(45度くらいの角度で)軽く差し込みます。ポンプを少し押して喉の奥の方向に少量の流動食を流し込みます。手を緩めて少し楽な格好で飲み込むのを確認してください。自力で「ゴックン」と飲み込んでくれればOKです。
- 自力で飲み込まない場合は、顎を少し押し上げて顔をさらに上に向けるようします。これでほとんどの猫ちゃんが喉の奥に溜めていた流動食を飲み込みます。毎回、喉の「ゴックン」という動作を確認しながら、注射ポンプを使って少量ずつを何回も与えてください。
- 無理に流し込むと誤嚥や吐き戻しの危険があるため、一度に多くの量を与えず、猫のペースに合わせて給餌しましょう。必ず少しずつ与えてください。
- 強制給餌で口の中に送り込む量は1回に0.5ml〜1ml程度、1回の強制給餌の総量は5ml程度から開始し、徐々に増やしていくのが良いでしょう。1日4〜6回に分けて与えましょう。
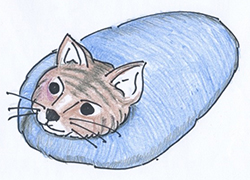

強制給餌を行う場合に最も注意する事は、喉奥に多くに流動食を一度に流し込まないように、少しずつの量を、ゆっくりと与える事です。無理して一気に1回量を多く流し込むと気管に流れ込んで誤嚥性肺炎の原因となります。
注射ポンプは繰り返し使用していると滑りが悪くなります。そのようになったら新しい注射ポンプに交換してください。また、水を飲ませる場合も同じように行なってください。
強制給餌に必要な注射ポンプは動物病院で分けてもらえます(必要な方は当院受付に申し出てください)。また、流動食やそれに変わるリキット製品も動物病院で入手可能です。
強制給餌の実技に関しましては、猫ちゃんと一緒に来院してもらえれば実技指導を行います。また、インターネットで「猫の強制給餌」と検索いただければ、いくつかの動画が見られますので、そちらも参考にしてください。
2)排泄の介護:おむつ
寝たきりで立てなくなり、自力でトイレに行けなくなった状態では、積極的におむつの利用を検討しましょう。猫用のおむつも市販されています。最初は嫌がる子も多いですが、慣れるとケアがとても楽になります。ただし、おむつは蒸れによる皮膚の炎症が怖いので、こまめにチェックして、少しでも汚れていたら交換します。そうすることによって陰部/肛門周囲の汚れ、蒸れを予防できます。長毛の猫ちゃんでおむつを着ける場合は、お尻周りの毛をカットするとお手入れも楽になり、皮膚トラブルのリスクが下がります。
3)床ずれの予防
寝たきり生活を送っている場合は、できるだけ伏せの姿勢(肺が最も拡張し呼吸が楽な姿勢)で過ごさせるように工夫をしてください。横臥姿勢(横向きに寝ている姿勢)でしか過せない場合には、2〜3時間ごとに右下の横臥姿勢から左下の横臥姿勢へと体位を変えてあげてください。このような体位変換をすることで、床ずれの発生を予防し、また、左右の肺の拡張を均等に呼吸を楽にしてあげられます。
床ずれ(褥瘡:じょくそう)とは、持続的な皮膚の圧迫により血行が悪くなり皮膚が傷つき、ひどくなると皮膚に穴が開き細菌感染を起こした病変(潰瘍)です。
床ずれは、頬・肘・肩・腰など、骨が出っ張っている所で起こりやすいため、赤みが出たり毛が薄くなったりしていないかをこまめにチェックしましょう。床ずれの気配が見られた時には、その部位の下にクッション性の高いタオル・毛布や介護用マットを敷いてあげてください。皮膚に穴が開いたような病変(潰瘍病変)が見られたら、すぐに動物病院での治療を受けるようにしてください。
4)マッサージ
寝たきりになった高齢の猫ちゃんの血行を促すために、からだ全体を優しく、ゆっくりとマッサージをしてあげることも大切です。マッサージは猫ちゃんとのコミュニケーションにもなりますので、ストレス軽減にもつながると考えられています。ただし、痛がる素振りを見せた場合は、すぐにマッサージを中止して、獣医師に相談するようにしてください。
5)寝る姿勢
寝たきりの場合は、唾液などの誤嚥を防ぐため、頭が少し高めになるように枕やタオルを頭の下に置いてあげるようにしてください。嫌がる猫ちゃんの場合は、食後1時間だけでも頭は高めの位置に保っておきましょう。




































